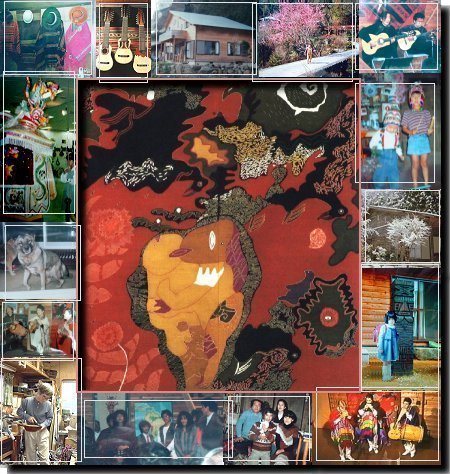
カバーニャ誕生のいきさつを知らなければカバーニャの本当の姿は見えてこない。
福岡 稔 小伝 ●小林隆雄
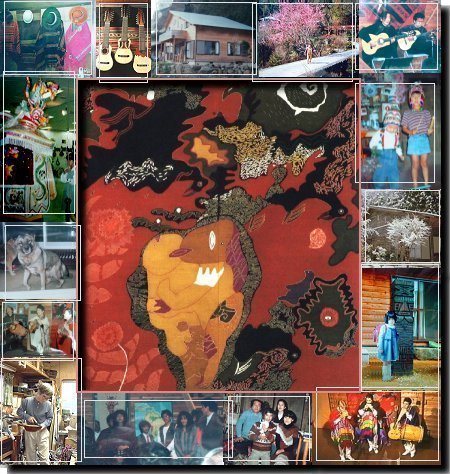
カバーニャ誕生のいきさつを知らなければカバーニャの本当の姿は見えてこない。
福岡 稔 小伝 ●小林隆雄
| ■ボリビアの情報がない、音源がない、楽器がない! 福岡稔がチャランゴの製作を、妻の麻由美がアンデスの染織を学ぶために、初めてボリビアの地を踏んだのは、1976年のことである。 1970年代の日本は、フォルクローレ・ブームの最初の時期であった。商業音楽上のフォルクローレという呼び方や分類は、第2次大戦後にアルゼンチンから始まったもので、アルゼンチン北西部や草原部の音楽に代表されるものであった。60年代までの日本では、それほど広く知られていたものではなく、少数だが熱心な愛好家たちが、アタウアルパ・ユパンキ(64年初来日)やアバロス兄弟(66年に1度だけ来日。ケーナ上演の初渡来だったらしい)、ロス・キジャ・ウアシ(72年初来日)、ロス・チャルチャレーロス等のアルゼンチン音楽のレコードを愛聴していた。当時新たにファンになった者は、中南米音楽研究のパイオニアたちの記事を、唯一の専門雑誌『中南米音楽』からむさぼるように読み、数少ないレコードを探し回った。 やがてラジオからもフォルクローレの音色が聞こえるようになり、レコードも少しは入手できるようになった。こうして、戦前から主流であったラテン・タンゴに、ようやくフォルクローレが中南米音楽の主ジャンルとして加えられてきた。だから、そのころのファンにとってフォルクローレのイメージとは、パジャドール(吟遊詩人)のギターと歌、ガウチョ姿の男っぽいコーラス、歌手と楽団、アコーデオンの音色、等々……なのである。 しかし70年代に入るとこの流れは大きく変化する。特筆すべきことは、アンデス音楽がフォルクローレの中に、というよりむしろ商業音楽の中に、地位を得たことであろう。1970年の「コンドルは飛んでいく」のメジャー・ヒットが、フォルクローレに興味を持つ新たなファンを生み出したことはまちがいない。70年代中期はかなりの数のフォルクローレ盤が国内出版され、新譜が毎月レコード店に並んだが、それらの多くはアンデス音楽であった。おそらく、古くからアルゼンチン北西部や草原部のフォルクローレを愛好する人たちは、唖然としたであろう。 しかしこの現象は、中南米音楽に新たなファンを呼び込むことになった。これらのアンデス音楽は大半がケーナを中心とするもので、フォルクローレ・ブームというよりは「ケーナ・ブーム」というべき性質のものであった。これは、ヨーロッパにおける60〜70年代のアンデス音楽の動向とほぼ同じであるから、本場南米諸国の事情はともあれ、国際市場での商業音楽の傾向であったのだろう。だが日本人には「言葉の壁」がある分だけ、ケーナの演奏ものに好みが集中したと見ることもできる。 さらに重要なのは、このアンデス音楽愛好熱はレコードを鑑賞するだけではなく、自分たちも演奏するという強い傾向を持っていたことである。この現象はかつてのフォーク・ブームと似ているが、ほとんど和製化しなかった。本場のスタイルをコピーあるいは踏襲し、できれば本場に同化しようとした「本物志向」は、ウェスタンの愛され方に似ているが、演奏したいというファンが増大したのは、ケーナという楽器のおかげであろう。 福岡がケーナの東出五国とともに「ロス・コージャス」を結成したのは1974年で、これがおそらく日本最初のアンデス・ボリビア音楽の演奏グループである。 福岡は、ケーナより、のちに「それは虹色の音色だった」と語るチャランゴに強く惹かれ、手を尽くしてようやく楽器を入手すると、その奏法研究に取り組んでいたのであった。もちろん先人はいないのだから、まったくの手探りである。ブームのおかげで徐々に来日が増えてきた南米の演奏家を宿舎に訪ねては、本場の奏法を学び取り、さらにはチャランゴの自作にも取り組むようになっていた。ロス・コージャスを結成して演奏活動を始めると、やがてそのあとを追うようにいくつものアマチュア演奏グループが誕生し、アンデス音楽のコンサートが開かれるようになった。フォークからの転向組はギターが弾けたし、中にはウクレレからチャランゴに移行した者もいて(福岡がそれである)、グループでの演奏熱は急速に高まった。 しかし福岡は、違和感をぬぐいきれなかった。それは、最初に福岡を強く惹きつけたボリビアのチャランゴの、その向こうに見え隠れするボリビア音楽の世界に、どうしても手が届かないからである。そのころ『中南米音楽』ではアンデス楽器の輸入頒布も始めており、新興アンデス音楽勢力にとっては、他にはない貴重な入手ルートであった。しかし、楽器やレコードはほとんどアルゼンチンのもので、福岡が追い求める生粋のボリビアの音楽はあまりにも稀少であった。福岡はついに、自分でボリビアに出かけなければと決意する。チャランゴの故郷ボリビアで、本格的なチャランゴ製作技術を体得するためである。 この当時ボリビアの情報が少なかったのは、おそらく次のような事情によるものであろう。ボリビアの音楽状況は、アルゼンチンやブラジルなどの商業音楽市場に比べるとまだ規模が小さく、アンデス諸国ならペルーの方が一歩リードしていた。現に福岡ですら、自分に衝撃を与えたチャランゴ奏者エルネスト・カブールの演奏を、ペルー盤とアルゼンチン盤によって聞いたのである。少しずつ知られるようになったボリビアの演奏家たちは、南米人の混成グループに加わってヨーロッパ等で活動しており、アルゼンチン盤やフランス盤などでも、生粋のボリビア音楽グループは少数であった。もちろんボリビア盤を入手するのは極めて困難だったのである。現在の感覚でいえば、豊富な音源がボリビア国内に「未発見」で眠っていたと考えるかも知れないが、実際は、私たちが思っていたほど豊富にあったわけではない。やがて福岡はその実情を目にすることになる。 退職・ボリビア渡航・結婚を一度にやってしまう、という大胆な行動が始まったのは1976年6月、おりしも「コンドルカンキ」(アルゼンチン在住のボリビア・グループ)が来日中で、その舞台こそ本格的なボリビア・フォルクローレの日本初上演であったというのも、あまりにも奇遇であった。 |
| ■カブールとの絆、ガンボアの工房での修行、そして日本に「アンデスの家」を 1976年のころはボリビアへの観光旅行者などはまず考えられず、技術・学術や商用の関係者がわずかに赴く程度であったから、旅行案内のガイドブックなどはもちろん、地図さえなかなか入手できなかったという。周囲から「とんでもないことだ」と引き止められたが、引き止めるのが当然であった。今では若者たちがアルバイトで旅費をためて簡単にボリビアやペルーへ出かけてしまうが、当時はまだ海外渡航も制限があり、1ドルは360円の固定相場の時代、しかも比較的渡航しやすいアルゼンチンならともかく、ほとんど未知のボリビアへである。もちろん、一番不安を覚えていたのは当の二人であったはずである。 地球を半周し途中で病気をしたりしながら、ようやくラ・パスで出会えたエルネスト・カブールは、二人の知っている顔と違っていた。日本で紹介されている写真は別人のものだったのである。カブールは、60年代にフランスで活動する南米人音楽家たちに大きな影響を与えた「ロス・ハイラス」のチャランゴ奏者だが、ボリビアで後進を指導し、フォルクローレの地位向上・普及の活動をするために、一人フランスから帰国していた。一時期は演奏活動をほとんど行っていなかったようで、少数の熱心なファンから「幻の名演奏家」と呼ばれ、実態はまったく知られていなかったのである。このときから、福岡とカブールの長く深い縁が始まる。福岡の通信がボリビアから雑誌『中南米音楽』に寄せられ、日本のファンたちは、カブールの素顔の写真を初めて目にすることができた。 やがて二人は谷間の都市コチャバンバに居を構えた。各地のいくつもの楽器工房を見学した末、この地のチャランゴ工人レネ・ガンボアの作品や製作姿勢に共感したからである。コチャバンバでの二人の日課は、夫は楽器工房へ修行に、妻は郊外のカンペシーナのおばさんのところへ機織に……であった。 麻由美は画家の父の薫陶を得て、幼いころから美術に才能を開花させていたが、アンデスの文様や色彩に強く惹かれていた。父も音楽を好み、弟の木下尊惇少年は当時「最年少のケニスタ(ケーナ奏者)」などと呼ばれていたから、福岡とは出会うべくして出会ったといえるだろうが、まさか地球を半周したアンデスの山中で新婚生活を始める、などとは予想していなかったのではなかろうか。そして、予想もしていなかったことに遭遇したのは、ボリビアの人々も同じであった。おれたちの音楽や楽器を勉強しに、日本から来るヤツがいるなんて……シンジラレナイ! 福岡が目にしたのは、人々の貧富の差が激しいこと、貧しくても力強く生きていること、フォルクローレの社会的地位が思ったより低いこと、だからカブールたちがフォルクローレの地位向上・普及運動を強く推進していること、等々であった。 ボリビアでも北米やヨーロッパのポップスの力は強かった。民族音楽は日本の民謡に比べればはるかに大衆的だが、楽団、オルケスタによるダンス音楽や歌が多かった。日本人が「これぞフォルクローレだ」と思っているものは、ヨーロッパからの逆輸入で盛んになってはいるが、それらのうちの一つのスタイルでしかなかった。 さらに福岡が見たのは、フォルクローレの奥の深さであった。日本ではほとんどケーナの音楽のように思われているが、笛類だけでも実にさまざまな楽器が用いられており、中でもサンポーニャの種類と奏法の多彩さには目を見張るものがあった。弦楽器の種類も豊富で、調弦や弾き方も複雑多種であった。レコードで聞ける都会的なステージ音楽だけでなく、郷土色の濃い、ほとんど民衆の中でしか演奏されないような音楽がたくさんあり、こういうものの録音はとても少なかった。祭りにはバンダ(吹奏楽団)がフォルクローレの曲を演奏しながら練り歩いた。 ラ・パスにはカブールの弟ルーチョがいた、クラルケンやフナロ兄弟もいた。サビア・アンディーナはようやく人気が出始めたころであったし、スクレにはマシスがいて、コチャバンバにはカナタや若きカルカスがいた。ベテランたちにまじってさまざまな新しい才能が開花しようとしている熱気を、二人は強く感じた。 やがて福岡は、これらですらボリビアのフォルクローレの一部でしかないことに気づく。かつて一世を風靡したロス・コリィ・ワイラス、ペペ・ムリージョ、エンバハドーレス等のクリオージャ音楽、ニーロ・ソルコやモントネーロス・デ・メンデス等の、アルゼンチン音楽と共通性を持つ南部音楽。グラディス・モレーノやトリオ・オリエンタルが歌う東部サンタクルス地方の芳醇な音楽、あるいは、低地亜熱帯の地域にも独特の音楽がまだまだあるらしいこと……。 こうして福岡は、自分が夢に見たボリビアのフォルクローレの全貌を、ようやく強く抱きしめることができたのだ。 貧しいながらも明るい民衆の日常の中に、きらきらと輝く豊かな音楽を感じ、荒削りで美しい技巧ではないが香りあふれる音楽性が満ちているのを、ボリビアの人々とともに体験できたことは、何物にも代えられないものであった。二人の下宿には、珍しい日本人に会いに毎晩のように人々が集まり、楽器を演奏した。そんな中に驚くほど巧みなチャランゴ弾きの少年がいて、夫婦と親しくなった。それがアレハンドロ・カマラであった。 あっという間の1年が過ぎ、滞在資金も先が見え始め、二人は帰国することにした。多くのことを学んだが、それでも学び足りない気持ちは残った。このころ福岡は、自分が修行するだけではなく、日本のファンにもっとボリビアの音楽を、ボリビアの人々の暮らしや思いを知って欲しいという思いに取りつかれていた。アルゼンチンのアンデス音楽やヨーロッパ好みに洗練された音楽ばかりではなく、力強く泥臭くたくましいアンデス音楽が、ここボリビアにあるのだぞ! と叫びたかったに違いない。 その思いはやがて、自分自身が大きな荷を背負うこととなってしまう。ボリビアの良い楽器、日本では入手できないレコード、美しい織物……。それをいくら紹介したくても、日本での引き受け手を確保しなければならない。残念ながらそれは実現しなかった。1年間もともに過ごしたボリビアの人々の、「ミノルとマユミはきっとおれたちの音楽を日本に紹介してくれるぞ」という無言の期待を背に、二人は日本に帰ってきた。 二人は神奈川県の南西部、酒匂川の流れる山北町に小さな家を借りた。あたりの景色がコチャバンバによく似ていたからだ。結局、ボリビア音楽の普及紹介活動は、自分たちでやるしかないと思うに至り、この家を「アンデスの家ボリビア」と名づけた。居間には、ボリビアにいたときのように、麻由美が使う手織りの織機が立てかけられていたが、チャランゴ、ケーナやサンポーニャ、各種の笛、打楽器、そして織物や民芸品は、もはや自分たちが深く愛するものたちにとどまってはくれず、輸入し販売する商品へと変質してしまった。 おかげで日本のアンデス音楽ファンは、初めて目にして手で触れられるボリビア音楽の世界に、涙を流して(本当に流して)喜んだ。伝説のマウロ・ヌニェスが弾くチャランゴを聞くことができた。細めのアルゼンチン・ケーナに親しんできた者は、太いボリビア・ケーナを吹きこなそうと必死になった。あの幻のカブールの顔が大写しになったジャケットのレコードやチャランゴを手に、長時間二人の話を聞き、飯を食べさせてもらい、ときには泊めてもらったりもした。買い込みすぎて支払いが足りなくなり、後日払いをお願いする若者たちもいたが、たいていそういうときは、福岡はニヤニヤしていた。 福岡と麻由美は、全国各地でボリビア展を開いた。東京・銀座の真中で開かれた展示会には一陣の清涼な風を感じ、厳寒の帯広から届いた麻由美の頼りなげな手紙からは、凍てついた冷気が吹いてきた。展示会は小さなものから大きなものまで各種だったが、それまでボリビアという国をほとんど意識しなかった日本人には、新鮮な驚きだったろう。 しかし、このころの福岡の心情には揺れがある。自分はボリビア音楽の愛好者であり、輸入業者になりきるつもりはない、という気持ちと、ボリビア音楽を深く知っている自分(筆者は、当時唯一の存在であったと今も思っている)が紹介しないで、だれができようか、という思いのはざ間で揺れている。周囲はほとんど気にもとめないことなのだが、福岡の思考、福岡の美学にとって、これは二律背反的な大きな問題であった。本来の目的はボリビア音楽をもっと知ってもらうことだ、しかし食うためには稼がなければならない、他の仕事で稼ごうとしたら普及紹介活動などというものはできなくなるから、ボリビアの人々の期待に応えてレコードや楽器を売るのが理にかなっている、しかし商売的ではありたくない……。このジレンマを察した幾人かの客は、「分けてもらう」というスタンスを取ることで、お互いの心の平安を得ることができた。福岡の心情がよく理解できたからだ。 |
| ■別れと再起 現在の「アンデスの家ボリビア」は、山北町のとなり、曲がりくねった急坂をいくつも越えた松田町寄(やどろぎ)にある。山を背にした狭い河岸段丘の上に建物が建っている。1984年にここに移ったのは、客が泊まりがけで来ても余裕があるように、夜中に楽器の音を出しても近所に迷惑をかけないように、という理由であった。しかし福岡の考えの深層はそうではないと思う。おそらく商売と紹介普及活動を秤にかけたら、後者が重かったのだ。だが寄までの交通の便は悪く、当然、熱心なファン以外の客の足は遠のいた。 このころから福岡は「アンデスの家第2次計画」を口にするようになる。それは、小ホールのようなスペース、PA機材、宿泊施設を備えた建物の建設である。もともと居住する建物も、わずかな人手を借りたがほとんど自力で建てたようなものであった。音楽用(客用、ファン用とも言える)には配慮が行き届いていたが、建築費用は極力押さえたもので、潤沢な資金を持っているなどとはとても思えなかったのだが、さらに新館の建設とは、と周囲は驚いたのであった。 福岡は「鉄道の枕木が」とか「廃材を……」と熱っぽく語り、そこへ福岡を強く支援する人が「あそこの銭湯を解体するそうだ、すごい梁が手に入るぞ」と駆け込んだりと、不思議な光景が見られた。麻由美が「こんなことをしたって、結局ほとんどわかってはもらえないのにね」と、愛犬の頭をなでながら呟いたが、眼の奥には、やんちゃな駄々っ子の話をしているような笑みが光っていた。麻由美も、夫と同じ夢を見続けていたのである。 しかしこの壮大な夢は、一朝一夕には実現しなかった。いかに自力で建てるとはいえ、経費は並大抵のものではなかったし、夫妻で交互に病に倒れたからである。 いくつもの問題を抱えながらも、二人はこの間数度のボリビア行きを繰り返し、「アンデスの家ボリビア」にはさまざまな人を迎え、温かなひとときを提供した。ボリビアからはエルネスト・カブールたちやカルカスのメンバー、ボリビアで音楽修行をしていた木下尊惇の友で、麻由美には弟のようにかわいがられたフェルナンド・ヒメネス少年、木下尊惇・セノビア夫妻等々、多彩なアーティストたち、そしてもちろん、首都圏をはじめ遠くは九州、北海道から熱心なファンたちが来訪した。地元の小学生たちが福岡の指導で、日本ではめったに演奏されない土着性の濃い演奏を行い、谷間を渡っていく音色をテレビ・カメラが追いかけた。 麻由美の創作もこの時期に大きく進展した。家のすぐ前を流れる虫沢川の冷たい流れで夫に染色の洗いを手伝わせ、楽器製作で磨いた木工技術で木枠やパネルを作らせて、染織の大作を数点創りあげた。これらの作品はこの数年後、予期せぬ形でカブールやフェルナンド・ヒメネス、ルス・デル・アンデ、木下尊惇らのレコード・ジャケットを飾ることになるのだが……。 思えばこの時期が、二人の最も輝いていた時期だったように思う。商売としてはそれほどでもないようだったが、二人の夢はときどきちょっと回り道をしながらも、着々と歩んでいた。 時が流れ、結婚10年目にして初めての子供が誕生。二人はもちろん周囲もとても喜んだが、カブールの再来日公演が迫るころ、二人は再び病に倒れた。福岡が育て支援してきた地元の愛好会のメンバーが必死に地元公演の準備を重ねるのを、福岡は病床から助言し、指示し、ときには叱咤した。しかし退院後も事態は好転せず、麻由美の病は一進一退を繰り返した。ファンへの対応も十分なものができにくくなっていたが、福岡はかなり無理をしながら努力していたようだ。 折悪しく、ボリビア音楽関連の輸入販売業が次第に増え、客足はさらに衰えた。二人の「アンデスの家ボリビア」開設によって、日本のアンデス音楽の愛好は急速にボリビアに傾斜し、80年代にはほとんどボリビア一色となっていたから、同業の人たちが出現するのは時間の問題であった。しかもその多くは(ほとんどは、かも知れない)ビジネス・レベルで営業を始めたから(これも当然である)、福岡の流儀では分が悪かった。東京都内で簡単に入手できるなら、それで用が済む客はわざわざ足柄の山奥まで足を運ぶ必要がなくなったし、客の側も世代交代が進み、あれほど貪欲にボリビア音楽の情報を求めた往時のファンの熱気は、情報が豊かになるにつれ、あるいはボリビア渡航が容易になるにつれ、次第に過去のものとなった。大学生のグループが少しずつ増え始めたころ、当時の主だった連中に学生交流会を作ることを強く勧め、並大抵でない援助を注いだことも、学生たちが代替わりすると次第に忘れ去られた。最近フォルクローレ・ファンになった者にとって福岡の存在は、1977年当時に比べれば驚くほど遠いものになっていた。 1991年夏、別れが訪れた。福岡麻由美、享年41歳。わずか3歳の娘を遺しての旅立ちであった。 福岡は失意のうちにも、娘の養育を考えて生家の吉祥寺(現在の吉祥寺店)に移り住んだ。父が営んでいた小さな文具店を改装し、そこに「アンデスの家ボリビア」の看板を移した。 しかしその生活も長くは続かなかった。「このままでは数ある輸入販売業の一つになってしまう」と悩み、迷い、もがいた末、自分の本拠はあの寄の「アンデスの家」で、自分が歩み続けるべき道は麻由美と二人でたどった道であり、しかし帰る以上はあのころの二人の夢を現実化しなければならない、と考えるに至った。福岡が再び本来の「アンデスの家ボリビア」に戻り、ボリビア音楽館の建設に独力で着手したのは、1993年春のことである。 |
| ■「夢ふたたび」は遠い夢か 1993年の秋、ボリビア音楽館「カバーニャ」が完成した。こけら落しは、木下尊惇が率いる「ルス・デル・アンデ」のコンサートで、亡き姉に捧げる追悼演奏でもあった。その後ほぼ隔月、会員制の愛好会「クルブ・カバーニャ」によってコンサート活動が続けられている。アレハンドロ・カマラも、麻由美に会うには遅すぎたが、この家を訪れた。 しかし現実には、福岡が、そして麻由美が夢見たほど、カバーニャは活用されていない。第一には、吉祥寺店との両立が土日のカバーニャの利用を阻害しているから、第二には、市場競争の現実は厳しいものがあるからだ。そしてさらに、福岡自身の意欲の減衰があることは否めない。 福岡の意欲減衰は、体調や疲弊、加齢によるものだけではない。自分たちが描いてきた夢は、本当にファンたちが求めていたものだったのだろうか、意味があったのだろうかという、自問自答の末である。自作のチャランゴも彫らなくなって久しい。自分が大切にしていることを仕事にした人間が時に陥る深い悲しみを思って、筆者の心は痛む。 そしてなにより、麻由美の不在は決定的であった。 福岡は、かつて商社マンであったというのに、あまり商売向きのタイプではない。日本におけるチャランゴの草分けであるのに、スポットライトを浴びるアーティスト・タイプでもない。どちらかといえば、頑固一徹に筋を通そうとする職人肌である。自分が販売したものでもないチャランゴの修理を引き受け、自分の気が済むまで徹底的に修理し、実費しか請求しない。しかしその大半は、実費割れを起こしているというのにである。一途で完全主義だから中途半端で終わらない。だからしばしば泥沼に足を突っ込む。 これは、「アンデスの家ボリビア」を多くの販売店の一つとして見るなら、頑固オヤジの店の姿である。「寄の仙人」などと噂されても、ただ苦笑するしかない。しかしそう見えるのは、福岡の本当のキャラクターとまだ出会っていないからである。福岡と麻由美が目指したものの片鱗にも触れていないからである。今の新しいファンでもカバーニャを訪ねて福岡と語り合えば、きっと今まで感じなかったものに出会えるはずである。 福岡の一途さが、実は日本国内だけでなく、本場ボリビアの音楽事情を動かす大きな力になっていたと思えるフシがある。1977年の二人の最初の帰国直後はさほどでなかったボリビア盤のレコードの点数が、徐々に増えていった。日本以外の需要は、アルゼンチン、北米、ヨーロッパが考えられるが、のちにボリビアにおける1回のプレス数を知って驚いた。当時のかなりの割合が福岡によって輸入されていたのである。日本のレコード需要の高さは有名だから、ボリビアのレコード出版事情は日本への輸出によってかなり促進されたと見ることもできるだろう。ボリビアでも若手演奏グループが急増するのは80年代に入ってからで、レコード等の音楽産業との相互作用で隆盛したのである。 もちろん直接的には、カブールたちが努力していたボリビアのフォルクローレの地位向上・普及活動の成果であり、背景にボリビア社会経済の安定や発展があるのだが、そこに福岡の介在を見ることは十分な確実性がある。日本国内における同業者の参入は、このようにしてボリビア音楽市場が豊かになったのちのことである。 同様の現象が楽器についても言える。2度目の渡航の際、福岡はチューニング・メーターを持参した。ボリビアの工人たちはおろかヨーロッパ経験のあるカブールさえも、初めて見る器械に大いに興味を示した。カブールが「こいつは正確でない。針がゼロで止まらず左右に振れているじゃないか」と言ったというエピソードさえある。みんなが欲しがるので、帰国後福岡は10台以上も購入してボリビアに送った。ボリビア製の楽器のピッチが驚くほど正確になってきたのは、それからである。かつては福岡が、販売前にかなり手を加えて調律していたサンポーニャも、微修正で済むようになった。同じ大きさだったケーナの指穴も正確な音階が吹けるように改良された。それらはこのわずか20年間に起こった現象なのである。これを「偶然重なったことだ。カブールたちの運動の結果だよ」と断じてしまうのは皮相すぎる。 シークやアンタラと呼ばれていた楽器を、「サンポーニャ」として日本に定着させたのも福岡である。シークはアイマラ圏、アンタラはケチュア圏の呼び方だが、カブールたちはスペイン語のサンポーニャを用いた。福岡もこの楽器のグローバル化の必要性をすばやく感じたのだろう。さらにサンポーニャと総称される笛には、大きなトヨ、キタ、サンカ、標準的なマルタ、小さなチュリ……さらに多数の区分と名前があることを、熱心に説いた。 このような福岡の事業と、先に記した日本各地でのボリビア展などの活動に対して、ボリビア政府は表彰を行った。本来なら外交機関や公的組織が行うべきことを、日本の一民間人が行っていることを賞賛したからだ。 こうして見れば見るほど、福岡の存在が、ボリビア本国のフォルクローレ事情に直接的に及ぼした影響が明らかになってくる。福岡の行動がカブールたちの運動の心理的な支援、強い味方となっていたであろうことも、十分想像できるのである。 これまでに記した事柄は、筆者が知る福岡稔と麻由美のすべてではない。しかし筆者が四半世紀にわたって見てきたものの主な事項を、できるだけ正確に描写したつもりである。福岡は最近、ファンに対して熱っぽく語る機会が少なくなってきた。少なくとも、アンデス音楽に関わる人々には知っておいて欲しい最低限の情報も、今の新しいファンにはほとんど伝わらない。福岡とは違った角度で、違った方法で南米の音楽を深く愛する筆者は、それを看過できなくなってしまった。だから、福岡がこれまで口にしたことのない、もしかしたら福岡自身も気がついていなかった部分も含めて、こうして記録に残すことにした。 福岡の生き方は尋常でないために容易には理解できない。でも少し角度を変えて眺めたら、大半の人間があきらめたり、捨て去ってしまった生き方と同じようなものかも知れない。この記録を読んでそう気づいてくれる人がいたら、福岡の「夢ふたたび」は、遠い夢のまま終わってしまうことはないと思う。 2001.1.31 ( こばやし・たかお proyectoffuma ) 2018年6月22日 福岡稔永眠 |
 |